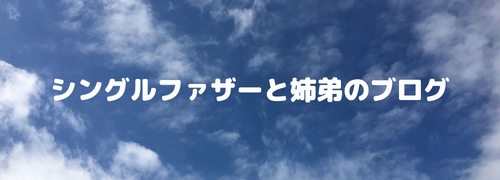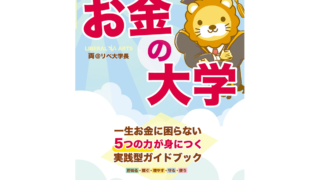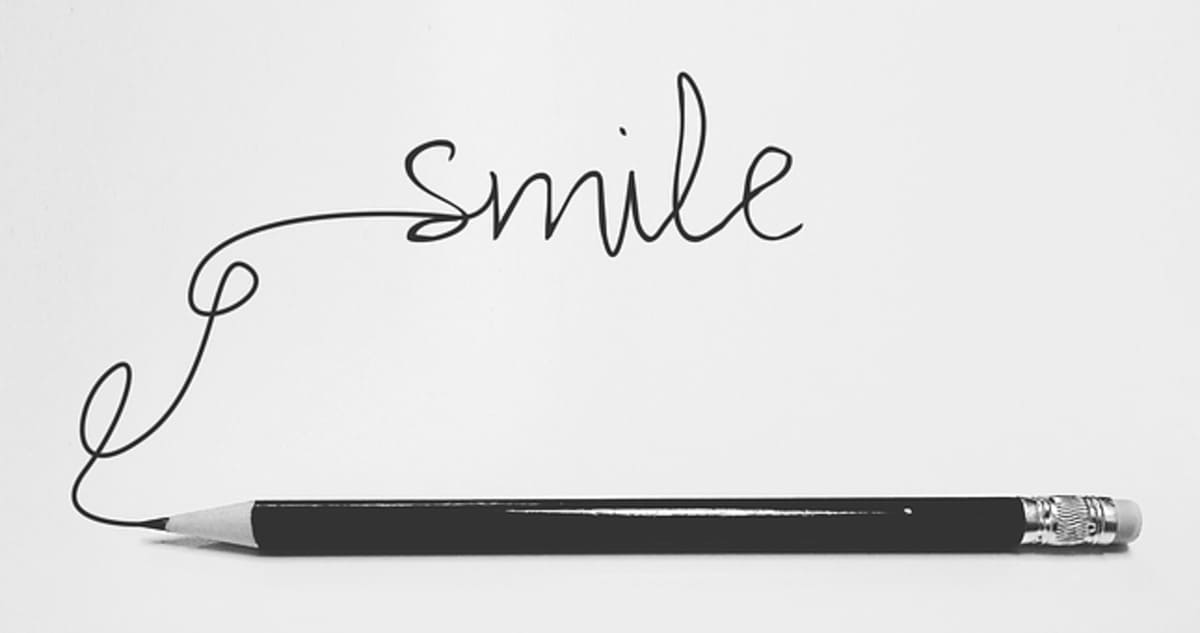- 離婚を子供はどう思っているんだろう?
- 子供への離婚の伝え方は?
- 離婚後は子供とどう向き合っていけばいいんだろう?
離婚をするとなった時に、親として考えるのは「子供の気持ち」です。
子供のことを大切に思い気持ちを考えるからこそ、悩んで不安になってしまいます。
✅この記事の内容
- 子供にとっての離婚
- 子供に不安を感じさせないための伝え方
- 大切なのは離婚してからの子供の気持ち
この記事では、離婚という選択をした大人だからこそ考えるべき、子供の気持ちや離婚の伝え方について。
そして離婚してからの子供たちとの生活について、子供の気持ちに不安を考える人向けに紹介します。
ぼくはシングルファザーとして、娘と息子と生活しています。
娘が5歳、息子が2歳の時に離婚を経験。
離婚をする前はもちろん、ひとり親となった今でも、子供たちの気持ちを最優先に考えるように生活しています。
離婚という選択をした親として大切なことは、「子供としっかり向き合う」ことです。
離婚した親としての大切なこと
- 離婚に対して子供は気持ちの準備ができない
- 新しい生活も前向きなイメージを伝える
- 大切なのは離婚してからの子供の気持ち
離婚したことで1番不安なのは、大人以上に子供です。
そんな子供と向き合うために大切なのは、親として離婚という現実を受け入れること。
そして、これから先の生活に目を向けてしっかりと考えていることになります。
親が離婚に対して不安を感じていたら、子供にも伝わってしまいます。
「離婚」という事実を子供に合った伝え方をし、これから先の生活が決してマイナスではないことを伝えてあげるのが大切になってきます。
子供とのこれからの生活を前向きに楽しんでいくためにも、子供と真正面から向き合うことが必要。
「離婚後の生活を前向きで明るいイメージ」にしてあげることが、離婚という選択をした親としての責任になってきます。
子供にとっての離婚

大人と違い、子供に気持ちの準備はできない
離婚をするとなった時に、大人は気持ちの準備はできても「子供に気持ちの準備はできません」。
ある日突然、ママやパパがいなくなるという現実。
これを小さい子供に伝えても、気持ちの準備などできるはずがありません。
離婚した時は5歳だった娘と、2歳だった息子。
年齢的な差はありますが、ママがいた生活の記憶も少しは残っているはずです。
親としては、離婚前以上にちゃんと向き合っていくことが大切。
大人であれば自分たちで気持ちの準備をして、新しい環境を受け入れる覚悟はできます。
小さい子供ほど、自分で気持ちの準備はできません。
だからこそ、ひとり親となってからの生活で子供の気持ちに寄り添っていく必要があります。
離婚をネガティブに思わせない生活が大切
子供に対して、「離婚したことをネガティブに思わせない」ことも大切になってきます。
「離婚」は、あくまでも大人の都合。
子供に「離婚が不幸」だと思わせないことも大切になってきます。
そのためにも、ひとり親として子供との生活をしっかりと考えていく必要があります。
- 生活費の管理
- 子育て
- 家事と仕事の両立
僕が離婚をする時1番つらかったのは、子供たちの気持ちを考えた時。
ママがいなくなってしまう子供たちを、かわいそうだと思ってしまった時もありました。
だからこそ、子供たちにそう思わせないような生活をいっしょにしていくことが親としての責任。
子供たちに離婚がネガティブなものだと感じさせないように、ひとり親としての生活を前向きに考えていく必要があります。
子供に不安を感じさせないための伝え方

親が現実を受け入れ向き合うことで、不安にさせない
親としては「離婚した現実を受け入れ、前向きな気持ちで子供と向き合う」ことが大切です。
離婚をして不安なのは、大人か子供か。
「離婚」ということに対して、気持ちの準備ができている大人と子供のどちらが不安を感じるでしょうか。
不安を感じる子供と向き合う時、親が離婚を受け入れ乗り越えていなければ向き合うこともできません。
親が不安ばかりを感じていたら、子供にも伝わってしまいます。
まずは親として離婚という「現実を受け止め」、「乗り越えていく」。
自分の中の不安な気持ちが子供に伝わらないように、「自分の中で前向きな気持ちを作っていく」ことが大切です。
子供に伝わる言葉で、前向きなイメージを伝えてあげる
子供に離婚を伝える時に大切なのは、「自分の言葉で子供に伝わるように」話すことです。
親として子供に離婚を伝えるのは、とても胸が苦しいです。
しかしそれが、ひとり親として子供と向き合っていくための第一歩になってきます。
僕の場合、5歳だった娘には自分の口から離婚を伝えました。
- 離婚をするということ
- 母親がいなくなること
- これからの生活が不安ではないこと
しかし「離婚を伝える」以上に意識していたことは、「これからの生活が不安ばかりでななく前向きだ」ということ。
子供が、離婚後に明るいイメージを持てるような伝え方を意識していました。
大切なのは離婚してからの子供の気持ち
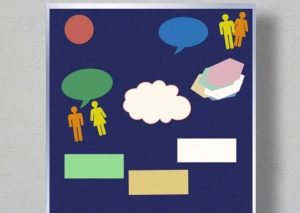
離婚は子供にとって大きな環境の変化
子供にとっては、離婚してママやパパがいなくなるだけで「大きな生活環境の変化」です。
環境が変わった時に苦労するのは、大人だけでなく子供も同じです。
そんな子供のためにも、離婚後の生活環境の変化を最小限にしてあげることも大切になってきます。
離婚にともなって、引っ越しを考える場合もあります。
引っ越しをする理由や状況については、人それぞれ変わってくる部分。
僕もシングルファザーになることが決まった時、実家への引っ越しを考えた時期もありました。
しかし娘にとっては、保育園が変わって先生やお友達も変わってきます。
家庭環境以外の部分でも、大きな変化に。
僕の場合、子供たちの生活環境の変化を1番に考えました。
その結果、このタイミングで引っ越しをするべきではないと判断。
離婚について子供の気持ちを考えるのであれば、離婚後の生活の方が重要。
子供にとっての生活環境の変化を、離婚以外を最小限にしていくというのも大切になってきます。
離婚した親として向き合っていく責任
離婚した親として、「子供の気持ちにしっかり向き合っていく責任」があります。
ひとり親としての自分の中で、「ぜったいに折れてはいけない芯」を作る。
これから先の生活で、子供とどう向き合っていくのかを決める部分になってきます。
今でも娘はたまに、母親を思い出す時はあります。
「ママ、元気にしてるかな?」
そんな時も、娘としっかり向き合って話をするようにしています。
それは「離婚」や「ママ」の話について、触れないようにするのも違うと考えているからこそ。
子供たちの気持ちを考えるからこそ、真正面から向き合って話をする。
大人からすると都合の悪い話だろうと、子供が納得するように向き合っていくのが離婚という選択をした親としての責任になってきます。
子供に対して離婚後の生活が前向きなイメージを与えたからこそ、ウソにならないように子供との生活を楽しんでいくことが大切です。
親として子供のためにできること
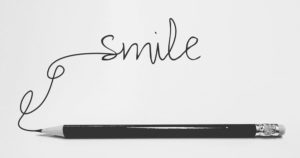
ひとり親としての生活が始まった後こそ、「子供としっかり向き合うことが大切」になってきます。
離婚した親としての大切なこと
- 離婚に対して子供は気持ちの準備ができない
- 新しい生活も前向きなイメージを伝える
- 大切なのは離婚してからの子供の気持ち
これからの生活に対して不安なのは、大人以上に子供です。
そんな子供と向き合うために必要なのは、親として離婚という現実を受け入れること。
そしてこれから先の生活に目を向けて、しっかりと考えることです。
親がこれから先の生活に対して不安を感じていたら、子供にも伝わってしまいます。
なので離婚という事実を子供に合った伝え方をし、これから先の生活が決してマイナスではないことを伝えてあげるのが重要。
子供とのこれからの生活を前向きに楽しんでいくためにも、子供と真正面から向き合う。
離婚後の生活が前向きで明るいイメージにしてあげることが、離婚という選択をした親としての責任になってきます。